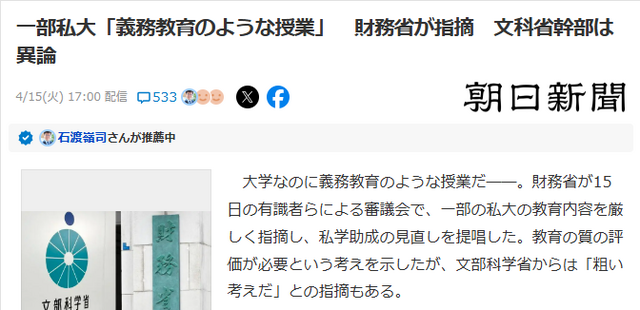財務省と文科省との綱引き。それぞれの言い分にそれぞれ一理ある。
大学に入ってから中学・高校で習うような基礎力を教えなおす・・・業界的には「リメディアル教育」という言葉が馴染みやすいが、そもそも「リメディアル教育」という言葉自体も事実をオブラートで包んで美化してごまかしているだけで、いわゆる中学・高校の「復習・補習」のようなもの。「そんなことが大学で起こっているのか・・・」と思われる方もいるかもしれませんが、偏差値60に満たない大学の学生さんなんかだと、得意・不得意などもありながら、特に英語が苦手な学生さんは話せない・読めない、その根拠が「中学・高校レベルの文法も単語もわからないから」ということになっている場合も多々あるでしょう。
例えば。私は30年以上前・・・もう30年で数え足りないほど年を取ったことに驚いていますが・・・当時の模試偏差値でいえば60くらいの某私立大学の法学部に合格、入学をしました。当時から今も変わらず私立のトップである早稲田大学や慶応大学の法学部は偏差値で言ったら70くらいだったでしょうか。現役当時は国語は不安定だった・・・というか古文・漢文いずれもノー勉で戦っていたので古文・漢文があたれば跳ねるけど、外れると・・・みたいな状況だったので英語と日本史だけで見ると、それでも65~67くらいはあった感じですかね。当時法学部で言うと早慶と中央という感じでしたが、今でいうところのMARCHみたいな感覚はなかったもんで、自分の学力で受かりそうなところ・・・と選んだ感じです。
では、偏差値65くらいあった人間の英語力ってどんなか・・・というと、ほぼ文法力は皆無、文法力がないので解釈もままならない。ではどうやっていたかというと、単語力と語法力・・・語彙力だけで何とかしていた・・・そんな英語力だったと思われます。それでも偏差値65くらいは取れるわけですから、偏差値60に満たない人の英語力なんていったら、会話は当然無理だとしても、簡単な英文の読解も難しいレベルでしょうね。本来であれば研究論文などを呼んだりしてより深い学びをしたい大学という場においてそれすらままならない。でもそれが大学生の過半数を占める・・・となれば財務省の言いたいこともわかる。そこに補助費を出すなんて無駄じゃないですか?と。
でも、その程度の学力の人間であっても社会に出て何とか働けているのも事実。ということは、大学を出ないと就職の機会が狭まる、大学は研究の場ではなく社会に出た際の役に立つ実学を学ぶ場である、と割り切ってしまえばそうなのでしょうが、本当はもっと研究の場であったほうが良い、みたいな感じなのかもしれません。ということは、もっと研究者の人たちが日の目を見るような環境を作ればいいのかもしれない。研究者が活躍して十分な生活ができるようにすることで、そちらをめざす人が増える。その人たちの研究によって社会が、経済がより良くなり、現場に出た人たちも十分に活躍できる・・・みたいな。すると、大学も今やポリシーを明確にしている訳ですから「うちは研究したい人を求めていますよ」「うちはより実務に近いことをやりますよ」みたいなことをより明確に打ち出して、その方針にあった学生を募集して育てていく、という流れをしっかりさせることの方が先決かもしれません。
とは言え、さすがに中学レベルの学習を大学でやる、そしてそこに補助金が出る・・・というのも決してスマートではないようにも思えますので、補助金をもっとドラスティックに分配しなおす、なども併せてやっても良いかもしれませんね。実学も大切ですが、より研究の方がお金がかかりそうですし。ですから、財務省と文科省が対決するような構図になるのではなく、それぞれが意見を出し合って建設的に今後の大学の在り方を整えていくと良いのではないかと感じました。子どもの数がどんどん減ってきている今、良い機会なのではないかと思います。